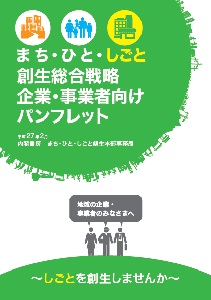2015年3月27日
【今回のキーワード/自己組織化単分子膜】
アルミニウム合金などの基板材料を有機分子の蒸気中に置いておくと、その有機分子と基板材料表面の間に化学反応が起こり、有機分子が基板表面に化学吸着します。 基板が分子によって被覆され、基板表面に反応できるところがなくなればそれ以上吸着反応が起こらないため、ナノレベルの単分子膜ができたところで膜の成長が終わります。 有機分子が自発的に集合して形成されるこのような薄膜を、自己組織化単分子膜と呼びます。 この反応では、膜を構成する有機分子を目的に応じて選択することにより、表面の機能性や反応性を任意にデザイン・制御することが可能となります。

名古屋市工業研究所の八木橋さん
名古屋市工業研究所のプロジェクト推進室研究員、八木橋信さんは、なごやサイエンスパークの先端技術連携リサーチセンターで産業技術総合研究所(産総研)中部センターと共同研究を行っています。 なにやら普通の公設試の研究スタイルとは少し毛色が違うやり方のようです。そのやり方とはどんなものなのか? また、彼はアルミニウムなど金属の表面に分子膜を処理することで、さまざまな特性を発現させる表面修飾の研究を主に行っているとか。 その研究がどんな分野でどのように使われているのか? さらに特許出願の目的と効果についてもお話を聞いてきました。
Q1八木橋さんは名古屋市工業研究所に来る前はどんなことをやっていたのですか?
(八木橋)
私は7年前に名古屋市工業研究所に入ったのですが、それまでは知り合いの興したベンチャー企業を手伝ってプロバイダのエンジニア、名工大で教員と、転職に転職を繰り返してここにいます。 ひとりで産・学・官の3つを経験することになってしまいました。

実験中の八木橋さん
Q2いろんな職種を経験して、ここでもその経験が生きているのでは?
(八木橋)
それがまたちょっと違います。実は私は機械工学が専門だったのですが、名古屋市工業研究所では機械とは直接関係のない電子技術応用研究室へ配属となりました。 入ってみたら初日から「化学をやれ」と言われて驚きました(笑)。全くの分野外でしたが、成果をあげなければいけないということで、とにかくがんばりました。ほとんどいちからの独学です。 共同研究者と話しをするにしても、まず言葉が分かりません。 「オクタデシル」とか「トリメトキシシラン」とか、最初は意味がまったく分からなくて、まずはそのあたりから本を読んで勉強しました。

実験で使用する薬品類
Q3どんな企業からどんな相談をされるのでしょう?
(八木橋)
具体的な企業名は守秘義務があるため出せないですが、本当に多くの業種の企業の相談に乗っています。 中小企業が技術開発の補助金を獲得できるのが理想的なのですが、中小企業では補助金申請の文書を書き慣れていない人も多いので、文書の書き方をアドバイスしたり、 赤入れしたりして申請の協力もしています。私はそこまで含めて支援だと思っています。単に研究室の中の実験だけでは終わらない、総合的な支援になります。 中小企業にとっては気楽に相談できる共有の研究員がいるという状態でしょうか。 中小企業の役員の方からは、まだ形がはっきりしていない状態でブレインストーミング程度の相談を持ちかけられることもあります。もとの話から脱線して、 いまの研究とは関係ない内容で補助金をとる流れになったりすることも。まあ、それはそれでうちの役割を果たしたことになりますから。
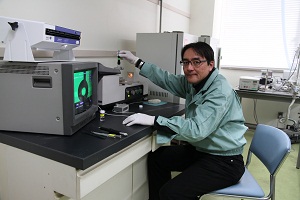
接触角の測定を行う八木橋さん
Q4そんな相談と共同研究の成果のひとつが、撥水や親水など表面修飾の技術ですね。これについて教えて下さい。
(八木橋)
まず疎水・撥水というのは、一時期、蓮の葉の表面を水玉が転がるような『超撥水』という言葉が流行りましたのでイメージしやすいかと思います。 撥液性を高めると、液体が表面に留まり続けるのを防ぐことができますので、防汚や防食の効果が期待できます。 普段あまり気が付かないところにも使われていて、たとえば薬品ボトルの内面なども、液体の切れがいいように撥水処理がされているものもあります。

蓮の葉の撥水効果
一方親水ですが、こちらはよく濡れるように、表面で水がつぶつぶにならないようにする処理。実は応用先としては、こちらのほうの問い合わせが多いです。 例えば、生体組織の硬さを映像化できる超音波顕微鏡用のシャーレはポリスチレンでできているのですが、そのままだと水を弾いてしまい、 超音波でスキャンする時に患部の組織がシャーレから浮いてしまいます。これを親水化することでそれを避けるのです。 濡れるシャーレがなかったときは界面活性剤(石鹸)を入れて親水状態を実現させていたそうですが、しばらくすると観察する組織の油脂が融けてきて、 急がないとだんだん映像がぼけてしまうという問題がありました。
そこでシャーレそのものの表面を修飾し親水化することで、長期的に安定して観察できるようにします。
Q5今日は実際に普通のアルミニウムと撥水処理を施したアルミニウムを用意していただきました。見た目はまったく同じなのに、こんなに特性が違うんですね。
(八木橋)
市販の薬剤で車のガラスを撥水にするときはもっと厚い層を作りますが、私の研究ではわずか数nmほどの単層の分子膜を作るため、見た目には何も変化がわかりません。 例えば、アルミニウムを蒸着した鏡にこの処理を施しても、見た目はもちろん反射率も一切低下しません。 アルミニウム表面には丈夫な酸化膜が覆っていますが、きれいに洗浄すると特定の構造を持つ分子が結合しやすい状態になります。 洗浄した表面を処理したい分子にさらすと、アルミニウム表面に出ている「手」と分子が結合していき、手がなくなればそれ以上の反応が止まるので、 ほぼ単層の数nm程度の膜が形成されます。この反応は自己組織化と呼ばれていて、厳密に処理時間や条件を制御しなくても、自然と同じ膜厚になるよう処理を施すことができます。

"撥水処理テストの様子(左が未処理のもの、右が撥水処理を施したもの)
このアルミニウムの場合は終端をメチル基(CH3)で修飾してあり、水は弾くけれどもエタノールは濡れるような面白い表面になっています。 だからエタノールでべとべとに濡れた表面を水できれいに洗い流せたりします。メチル基ではなくトリフルオロメチル基(CF3)にすると水も脂も弾くようになります。 つまり、材料の最表面をどの分子で終端するかで、表面の濡れ性を制御できます。材料本体の材質を大きくかえなくても、表面の数nmを変えてやれば、実用上の性質は大きく変わります。 分子膜はわずか数nmという薄い層なのですが、化学的にしっかりと結合していますので、母材が剥ぎ取られない限りは一旦着いたらなかなか取るのは難しいという強さがあります。
アルミニウムの場合とは異なり、分子が結合しにくい材料であれば、まず別の処理を施して基礎となる層をつくり、その上に目的の分子を処理することもできます。 表面の性質を変えるだけで材料本体を変える必要がないですから工業的にも取り入れ易い。処理に使う分子も様々な種類があり、 気がつかないかもしれませんがいろんなところで使われています。
化学を研究している人にとっては周知のことですが、機械分野の人たちは知らなかったりするという技術です。 だから私は、ちょうど通訳のように各分野の橋渡しをしながら、中小企業にアドバイスをしています。この撥水・親水の処理はそのほんの一部で、いろいろな企業から、 「表面がこんなに変わるならこんなこともできる?」というような感じでご相談をいただいています。
Q6そんな成果のひとつとして、半導体の電極配線として使われるアルミニウム合金に防食効果を施す技術で特許を取りましたね。これの特徴は?
(八木橋)
これが産総研との共同研究で得られた成果のひとつです。半導体のICチップへ配線する材料として広く使われているアルミニウム合金に防食効果を付与する研究です。 安価なICでは表面を樹脂で封止する『樹脂封止パッケージ』が多く用いられていますが、高温高湿度下に長期間さらされるとパッケージ内に水分が侵入して配線が腐食してしまうという問題があります。 そこで、私たちは配線自体を有機シラン分子の分子膜で被膜して耐食性を付与しました。ポイントとなるのは、処理前に真空紫外光(VUV)で表面を洗浄することです。 プラズマや高圧水銀ランプによる処理では、エネルギーが大きすぎて配線に傷をつけてしまったり、洗浄が不十分だったりします。 VUV光であれば汚れなどの有機物は強力に分解されるものの、素材を傷つけません。産総研のシーズは洗浄後、さらに気相法で1000Paの条件下で有機シラン分子であるn-octadecyltrimethoxysilane(ODS)の分子膜を付けるというのが特徴です。 この防食効果は塩水噴霧試験によって確認しました。わずか直径30μm程度のアルミニウム合金製の配線ですが、96時間塩水を噴霧した結果、処理していない配線は表面が完全に腐食してしまいますが、ODS分子膜で処理した配線は表面の光沢が維持され、電子顕微鏡で観察しても腐食していないことを確認しました。

オペアンプICのボンディングワイヤー
Q7従来の方法と比べて、シンプルで環境負荷も低いという特徴があるそうですね。
(八木橋)
はい、この方法は、有機シランと一緒に表面処理したいものを瓶に入れて蓋をしておくだけで処理できるので、特別高価な設備は要りません。 CVD(化学的気相法)となると設備も高価になりますが、この方法は機器の導入が手軽であるため中小企業向けだと思います。 もちろん100%欠陥がない分子膜を形成することは難しいので、完全に表面が覆われて恒久的に腐食を防ぐことができる、というわけではありません。 それに論文などで腐食の評価に使われる酸やアルカリの水溶液は強すぎて、そういう意味では「腐食しない」表面でもありません。

塩水噴霧試験後のボンディングワイヤの光学/電子顕微鏡観察(ODS皮膜)
ただ、塩水噴霧試験で4時間も持たずに完全に錆びて使いものにならないものを、96時間経過しても問題なく使用できる技術というのは、実用的であり魅力的です。 そんな実用的で、工業的な面から見たシーズ技術の落とし込みによって、今までより性能が良いという付加価値や、クレームの数を減らすなどの効果を狙えると思っています。 決して華々しい技術ではありませんが、生産ラインでいかにコストを下げられるか、不良品を減らせるか、そのために必要な投資を最小限にしながら改善を図るのに役立ちます。
Q8この志段味にある研究室は、産総研との共同研究が主だということですが、その経緯は?
(八木橋)
私が入った役割がまさにそれでした。つまり、『産総研と連携して、その研究成果を中小企業のために役立てる』ということ。 産総研は、国の研究機関として、新しい産業技術を提案するために、研究開発を進めていますが、すぐに研究内容を中小企業がそのまま活用するには難しいものが多いです。 だから中部センターが持つ研究成果を地元の中小企業に使って貰いやすくするというのが私の役割なのです。当所では『成果活用型共同研究』と呼んでいます。 つまり、産総研で出された特許や論文の内容をいかに実際の応用に落としこむか、というのが私の役割ですね。当所は熱田区ありますが、そこでは独自の研究も行っています。 ですが私はどちらかというと今ある技術をうまく応用して中小企業のために活用するためのつなぎ役をしています。 最初は技術相談で対応し、実際に提供された試料を処理するときには、技術指導として手数料をいただいています。
この特許の技術以外にも、いろんな研究成果を地元中小企業のために役立てているのですね。今日はありがとうございました。
取材後記
研究員でありながら既存の技術を巧みに利用して、相談を受ける中小企業のニーズに当てはめていく。八木橋さんのそのスタイルは、まるでソムリエやコンシェルジュのように旺盛なサービス精神に基づくものでした。 これは名古屋市工業研究所入所以前に大学や民間企業など幅広い職種を経験しているからかもしれません。もちろんそれには広い分野での深い知識が必要となります。八木橋さんの場合は新しい分野でも果敢に知識を身につけていきます。 そんな姿勢があるからこそ、中小企業からも信頼を集めているのでしょう。今後の特許戦略も含めて、八木橋さんの活躍に期待したいですね。
ワンポイント情報
平成26年12月27日に、「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン(長期ビジョン)」及び「まち・ひと・しごと創生総合戦略(総合戦略)」がとりまとめられ、閣議決定されました。 1.「東京一極集中」の是正、2.若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現、3.地域の特性に即した地域課題の解決 といった3つの基本的視点から取り組むこととしており、地域産業の強化のためには、新事業・新産業と雇用を生み出す地域イノベーションの推進が必要不可欠としております。 具体策としては、公設試と産総研の連携による全国レベルでの「橋渡し」機能の強化が、その役割を担うとされております。
まち・ひと・しごと創生本部別open_in_new[首相官邸ホームページ内]
本ページに関するお問合せ先
- 中部経済産業局 地域経済部 イノベーション推進課
- 〒460‐8510
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2774
メールアドレス:bzl-chb-sangi■meti.go.jp
※「スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。