2015年3月13日
【今回のキーワード/VFD (Vacuum Fluorescent Display=真空蛍光表示管)】
1966年に三重県伊勢市にあった伊勢電子工業株式会社(現ノリタケ伊勢電子株式会社)の中村正さんが世界で初めて開発したガラス管による表示装置。 ガラス板2枚に挟まれた真空部分にカソード(フィラメント)、グリッド(格子)、アノード(蛍光体)の三極構造からなる基盤が入っていて、 ここに電流を流すことによってカソードから放出された電子がグリッドで加速され、アノードに達し、塗布された蛍光体を発光させる仕組みです。 カーオーディオの表示パネルやデジタルサイネージ(電子看板)に使われています。 開発初期は蛍光体として酸化亜鉛(ZnO)が使われ、緑色しか表示できませんでしたが、その後発光体を硫化亜鉛(ZnS)に変え、さらに希土類のドーパント(賦活剤)を入れることでRGBのさまざまな色が出せるようになってきた経緯があります。

三重県工業研究所 井上研究員
VFDの実用例/自動車の内装ディスプレイ、屋外でのディスプレイ、寒冷地でのディスプレイなど
三重県で発明された技術のひとつに、現在も世界中で使われているものがあります。それがVFD(真空蛍光表示管)です。 1970年代から電卓やカーオーディオのディスプレイとして圧倒的なシェアで普及したほか、屋外表示板などに使われているというこの技術。 そのディスプレイで使用されている既存の蛍光体を改良して特許を取得したのが、三重県工業研究所の主任研究員、井上幸司さんです。 今回は彼の研究室を訪れ、そもそもVFDの特長はどんなところなのか、改良した技術によりどんなメリットが得られるのか、特許出願の目的や効果も含めて伺いました。
Q1VFDってLEDなどと比べるとあまり聞かない言葉ですが、実はいろいろなところで使われているんですね。
(井上)
昔のカーオーディオにはVFDが多く使われています。今ならプリウスやアクアのインパネ。あと高級仕様の車両には、ヘッドアップディスプレイの表示器としても使用されているんですよ。 車両のほかには給湯器の温度を表示させるパネル、スーパーなどにあるPOS、レジの金額表示。そんな場所でVFDが使われているのです。
Q2昔のカーオーディオに使われていたって聞くと、VFDはひと昔前の技術のような印象を受けますが、液晶と比較してのメリットってあるのでしょうか?
(井上)
VFDの最大の特長といえるのは耐環境温度ですね。
VFDは-40℃から85℃まで耐えられます。液晶や有機ELの場合はその耐環境温度の範囲が狭くなってしまいます。 北米やロシア、ヨーロッパなど寒いところのインフォメーションディスプレイの場合、液晶を使用すると素子の動きが鈍くなります。 VFDなら-40℃まで大丈夫なので、地球上で厳しい寒冷地でも使えるわけですね。ですから屋外で動く車両関係で使われるのです。 ロシアなどではエレベーターの階数を表示するディスプレイ装置に日本製のVFDが多く使われています。以上のとおり、寒い地域でも使えるという点がひとつ。 もうひとつは、自発光と非自発光の違いです。

VFD実施例/受付カウンターなどでのインフォメーションディスプレイ(出典:ノリタケ伊勢電子ホームページ)

VFD実施例/受付カウンターなどでのインフォメーションディスプレイ(出典:ノリタケ伊勢電子ホームページ)
VFD、EL、LEDやブラウン管テレビは自発光。一方液晶は非自発光です。非自発光の液晶は、バックライトが白色なので、カラーフィルターを通すことでRGBで発光できます。 ノートパソコンは太陽光の下では見づらいですよね。バックライトが太陽光の明るさに負けてしまうから。ですから液晶は屋外でのインフォメーションディスプレイとして使いづらいわけです。 一方VFDは自発光なので屋外でも使いやすいのです。ただし、VFDにも弱点があります。ガラスの板が使用されているので、ちょっと重いという点で液晶と比べて劣ります。 あと大型化しにくいというところですね。100インチの液晶というのは存在しますけど、100インチのVFDというのは存在しません。 というのは、VFDはガラスの板で挟んだ中を真空にしなければなりません。100インチのガラスの板を2枚用意してその中を真空にするとなると、耐圧の関係でガラスの厚みがすごいことになってしまいますからね。 小型のサイズで、室内外にも使えるということ。ですから屋内外の小型サイズのマーケットでVFDは勝負しています。
Q3なるほど。今後も必要とされる技術なんですね。では井上さんがそんなVFDの研究開発に取り組むきっかけはなんだったのですか?
(井上)
私たち三重県工業研究所は県内企業のパートナーとして、毎年『出前キャラバン』というのをやっています。企業に出向いて、「なにか技術的に困っていませんか?」とお話を聞いて回るんです。 今回の研究開発は、シーズありきのものではなく、企業ニーズから始まったものなんです。 平成16年ぐらいに県内企業であるノリタケ伊勢電子でお話を聞いた際、VFDに関して現状抱える課題を相談されました。 そもそもVFDはノリタケ伊勢電子株式会社の元会長、故中村正さんが発明した技術で、最初のVFDは蛍光体として酸化亜鉛を使って緑色のみを表示するものでした。 その後酸化亜鉛以外にも硫化亜鉛と希土類を使った材料にすることで発光波長を変えることに成功し、RGBを表示させることができるようになりました。 つまり、RGBの組み合わせでマルチカラー化できたわけです。ところが長年点灯していると、蛍光体が劣化してしまう問題が出てきました。 硫化亜鉛の蛍光体が長年電子線を浴び続けた結果、分解するためです。そこで、耐久性のある蛍光体を作ってほしいという要望でした。
Q4共同研究ではないけれども、県内企業の課題解決のために始まった研究なのですね。でもそんな難しそうな課題を解決できる見込みはあったのですか?
(井上)
実は酸化亜鉛の緑色蛍光体はほとんど劣化しないのです。それは酸化亜鉛が酸化物だからです。それがひとつのヒントでしたね。 たまたま私の専門がセラミックスで、この酸化物がまさにセラミックスですので、自分の得意分野じゃないかと。 そこで酸化物になにかしら結晶構造をチューニングすることによって、緑色だけじゃなく青色でも発光できる蛍光体になるだろうと考えました。
Q5では具体的にどういう技術で緑以外の蛍光体を開発したのか教えてください。
(井上)
まず酸化物で構成された青色の蛍光体の開発から取り組みました。青色の色純度の良い発光波長とは460nm(ナノメートル)ぐらいで、緑色が520nm。 酸化亜鉛は約500nmなので、ほとんど緑色に近い光で発光するのです。ですから青色の蛍光体を開発するには、酸化亜鉛の発光波長を短くすることで実現できると考えたわけです。 そこで酸化亜鉛のうち、亜鉛のサイトに同じ2価の金属であるマグネシウムを固溶させていきます。10個の亜鉛サイトのところを8個の亜鉛と2個のマグネシウムといった割合にします。 これが我々の材料設計です。亜鉛にマグネシウムを固溶させると、500nmの波長を低波長にすることができたのです。 禁制帯(バンドギャップ)が広がって、バンドをワイド化させるからワイドバンドというんですけど、ワイド化させることによってブルーシフト(青色化)します。 我々の知見では470nmぐらいまで発光波長をシフトすることに成功しました。これはほぼ青色ですね。 今まではVFD用青色蛍光体として硫化亜鉛で実現していたのですが、私たちはそれより耐久性のある酸化物を使って作ることに成功したというわけです。
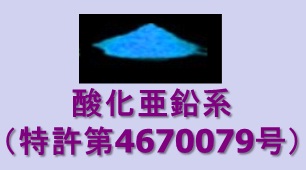
酸化亜鉛系(特許第4670079)
Q6亜鉛にマグネシウムという豊富にある材料を使っていることもポイントだとか。
(井上)
私たちとしてはマグネシウムというありふれた、レアアースではないもので耐久性のある青色蛍光体を開発したということも大きな特長と考えています。 一時中国がレアアースの輸出規制をして非常に問題になったことがありましたよね。業界が大変だった時期がありました。 実は私たちがこの開発を始めたときはそれより前だったんですが、そんな一件があって以来、注目されるようになりました。蛍光体の業界は、 ユーロピウムやセリウムといった希土類を使うほうが材料チューニングがしやすいので、今でも希土類が使われているのです。 従来品の青色蛍光体でガリウムを使ったものがあるんですが、それは高額なんです。やっぱり限りある資源を大切に使いたいということで。 私たちとしては地元の企業が手を出しやすい価格帯ということを考えて、『希土類フリー』という観点で蛍光体開発をしています。やっぱり高いものを使うのではなくコストも安く抑えたいと。
Q7そのような特長でまさに課題を解決したこの希土類フリーの青色蛍光体の技術、単願で特許も取っています。特許の目的と、その反響はいかがでしたか?
(井上)
反響としては、電話等も含めて数十件という、相当な数の問い合わせがありました。実際は特許というよりは新聞で取り上げてもらったことと、学会発表や論文の効果のほうが大きかったです。 学会発表の後にその場で質問を受けるんですが、そのとき質問者の方で、あまり突っ込んだ討議ができなかったのか、私が退席した後に走って追いかけてくる方がいるんですよ(笑)。 1対1で話す機会を窺っていたのでしょうね。「ちょっとここでは話しづらいので後で電話します」と名刺を渡されて。そういう問い合わせは主にメーカーの方ですね。 この技術はVFDだけでなく他のデバイスにも使えるのでLED関係の企業とか。 あとVFDのユーザーさんもサーベイ(調査)しているみたいで、「これを使うことでどうなった?」と、聞かれたことがありますね。さらに驚いたのは弁理士事務所からの問い合わせです。 私は当初「特許申請時はぜひともご利用ください!」というセールスかなと思ったんですが違うんですね。 どうやら海外の企業から委託を受けて、日本の技術を調査・集約して報告する仕事だったようです。 さすがに私たちは県内企業に役立つことが第一目的なのでお断りするんですが、特許を出してみて、初めてそういうビジネスがあるんだと驚きました(笑)。
Q8特許を取得したことでの効果はどうだったのでしょう?
(井上)
もちろん特許を利用していただくことを念頭に開発していますが、これはまだ製品化されていないので活用されていません。 ただ、私個人としては、やはり特許を取ることで県内企業さんへのアピールの手段のひとつになるんじゃないかと。 特許を取っていない、知的財産という概念の希薄な研究機関となると、企業も一緒に共同研究しようとはならないですよね。 いくらいい技術を持っていたとしても、特許に関心がないような研究機関では頼られないと思うんです。特許などの知的財産の経験と実績は、研究機関としては必須だと思います。 もちろん特許ひとつでVFD用蛍光体の技術すべてを覆えるものではないですが、知的財産を戦略として打って出るのは必要だと思います。
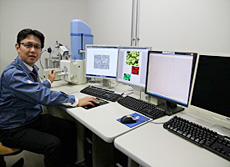
研究に取り組む井上さん/電子顕微鏡観察(ODS皮膜
Q9特許を取得することの違った一面を教えていただいた気がします。
(井上)
そうですね、さらに特許に関しては、取得する以前に利用する必要性があると私は考えます。 研究をやる前の段階で、日本国内のその業界の特許が今何件あって、どんな特許が押さえられているのかを見ることです。 それによって、今どういう分野がブームなのか、逆にどういうところにニッチな隙間があるのかわかります。熱心に研究されている分野やニーズの高い分野ほど特許が多く出されていますから。 研究テーマを設定する段階からそれを把握するのは大切ですね。その上で、自分たちの立ち位置がどこか? 県内企業の現況と照らし合わせて今なにができるか? 研究者である自分のポジショニングがわかってきます。企業から相談を受けた時に、「世界をみたときに、我々はこういう位置にあります。 技術的には残念ながらこのレベルですが、こういう支援ならできますよ」ということを明確に答えて解決方法を示すことができますので。 もちろんそういうやり方はマニュアル化されてないですし、私もいろんな人から教わったことを私なりに噛み砕いて吸収したことですので、これもまた正解はないと思います。
ともかく特許を出すだけではない、特許を見る力というのが研究者に求められるのかなと思います。
Q10地元企業の支援をする公設試の研究員だからこそ、そういうことも強く求められそうですね。さて、青色の発光体の開発に成功し、残りは赤色ですが、こちらは産官学の共同研究ですね。
(井上)
プロジェクト化してみようと取り組んだのが平成20年度のことです。 科学技術振興機構(JST)の研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)という事業に、「カラーメッセージディスプレイ用の高輝度酸化物蛍光体の開発」というタイトルで応募して採用されました。
弊所とノリタケ伊勢電子株式会社、共立マテリアル株式会社(名古屋市)、そして名古屋工業大学の4機関での共同研究です。 酸化物で青色蛍光体とともに赤色蛍光体を開発してマルチカラー化を完成させることが目標です。 名古屋工業大学が開発していただいた赤色蛍光体は希土類が入っていますが、耐久性のある酸化物で、酸化ガドリニウムを使用しています。 こうしてできたマルチカラーVFDで、実際ディスプレイを表示させるデモンストレーションができるところまでたどりつきました。 この三重県工業研究所の入口に展示しているインフォメーションディスプレイがそれです。まさに今回の技術を集約させて作ったマルチカラーVFDです。 USBで自由に入力した文字を配色できるようプログラムも組みました。

事務所入り口のカラーメッセージディスプレイ
Q114つの機関の共同研究という点では苦労された部分もあるのでは?
(井上)
研究進捗の維持・管理が一番苦労しましたね。 進捗会議は四半期ごとに開催してまして、そのたびに4機関が集まるのですが、計画とずれることもありますし、目標どおりいかないことがありますよね。 このときにわかったのは、フォーメーションを組んで役割分担をしても、最終的にゴールをみんなでしっかり共有してやっていくこと。 うまくいかないときは助け合う、やっぱり人間関係が大事だなと思いました。そして集まると毎回進捗会議後は必ず懇親会を開催してましたね(笑)。 でもそこで学ぶことができたのは企業サイドの開発スピード感や研究テーマの設定センス。「社会に貢献できる技術を実用化すること」という当然かつ重要な感覚ですね。
技術の重要性もさることながら、プロジェクトを進める手腕も井上さんの貴重な経験から習うところがたくさんありそうですね。今日はありがとうございました。
取材後記
研究テーマとなる技術が使われている背景や市場を的確に捉えた上で、地元企業のニーズを把握してそれに応えていく。 蛍光体を研究開発する井上さんは、まさにそんな役割を担う公設試の研究員のあるべき姿勢を徹底追求している人物であるという印象を受けました。 地元三重県で先人が産んだ世界に誇る技術だからこそ、同じ三重県の研究機関が受け継いで改良していくんだ、と井上さんは言葉にこそしませんでしたが、 そんな思いが伝わってくるようでした。特許を最大限に活用するという姿勢も見習いたいですね。
ワンポイント情報
(独)工業所有権情報・研修館は、平成27年3月23日から、特許情報について、高度化、多様化するユーザーニーズに応えるべく、「特許電子図書館」を刷新し、 新たな特許情報提供サービス「特許情報プラットフォーム(英語名:Japan Platform for Patent Information、略称:J-PlatPat)」を開設します。
従来の特許電子図書館(IPDL)に代わり、特許情報プラットフォームは、検索サービスの機能の充実化、ユーザーインターフェースの刷新、外部サービスとの連携、「色彩」や「音」等の新しいタイプの商標への対応、及び、 特許公報等の情報の一括ダウンロードサービス(民間情報提供サービス事業者向け)の開始等を行うことにより、意匠及び商標を含む特許情報を提供する新たな情報基盤としての役割を担うものです。
詳しくは特許庁のホームページをご覧ください。
本ページに関するお問合せ先
- 中部経済産業局 地域経済部 イノベーション推進課
- 〒460‐8510
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2774
メールアドレス:bzl-chb-sangi■meti.go.jp
※「スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。