2014年10月1日
【今回のキーワード/耐候性の評価】
第9回目は、名古屋市工業研究所に伺い、「耐候性の評価」について、その取り組みや、難しさ、さらに拡がりについて、研究者(丹羽主任研究員)に、お話しを伺いました。
規格が定まっている評価や、屋外に設置して直接製品を評価することなどは通常の試験として位置づけられていますので、方法は定まっています。
一方、規格のない新しいもの、特殊なもの、屋外では無く室内で使用するもの、短期間に長期的な劣化評価を行うなど、定まっていないものを評価するためには、 項目の設定や試験の方法、評価の仕方など、深い知識と経験が必要とされるとのこと。
工業研究所における「耐候性の評価」についてその全般的な活動についてご紹介します。
今回は、システム技術部品製品技術研究室 丹羽主任研究員にお話を伺いました。
Q1「耐候性の評価」とは、どのようなことを行っているのでしょうか?
(丹羽)
「耐候性の評価」とは、いろいろな使用状況に対する材料・製品の耐久性の寿命予測を行う事です。 評価のための規格があるものはそれに基づき実施すればよいのですが、評価の仕方が確立されていないものについては、 どういう試験を行えば目的とする評価と言えるのかまでを、一緒になって考え決めていかなければいけませんので、難しい評価と思います。
工場の外で、建材などの屋外曝露試験をされている光景を一般的に見かけることがありますが、これまでの当研究所では、 「建材」や「プラスチック」「塗料」など一般的なものも行っていますが、その他、「繊維製品」「印刷物」「トイレ」「パチンコ台のフィギュア」「LED照明」「広告物」、 そして、現在、中部地域や国内で盛んに製造に取り組んでいる「航空機部品」なども行っており、屋外で使用されるものだけでなく、あらゆるものが評価の対象となります。

丹羽主任研究員とサンシャインウェザーメーター
※耐候性とは、自然環境のうち主として日光、雨雪、温度、湿度及びオゾンによる劣化に対する抵抗性である(JIS D 0205 自動車部品の耐候性試験方法より)
これを求める場合に屋外曝露試験では、結果が出るまで長い時間がかかるため、人工光源を用いた促進耐候性試験が行われます。
Q2名古屋市工業研究所では、どのような評価ができるのでしょうか?
(丹羽)
当研究所には、いろいろな光源の試験装置が整備されています。サンシャインにキセノン、そして紫外線カーボンと、この3つを整備しているのは中部地域では当研究所だけです。 そして、製品や材料の劣化を判定するので、光沢度測定、色彩計測や、引張強度、曲げ強度などの物性試験も連動して実施します。
さらに、顕微赤外イメージングシステムなどの最新の機器も用いて素材自体まで踏み込んだ評価を行うことができますので、ものによってではありますが、単なる部品の評価ではなく、 素材自体の評価にも繋がっていくことで、材料の選定にまで遡った情報を収集することができると自負しています。
そして、評価装置も比較的大きなもの(300mm×300mm)にも対応できるので、部品丸ごとの評価などもできます。

耐候性評価試験装置

赤色塗料の劣化の比較写真

試験で劣化した樹脂の比較写真
Q3求められる評価はとても難しいと思うのですが、どのように進めていくのでしょうか?
(丹羽)
まず、最初は電話で結構ですので、当研究所に「ご相談」下さい。
自社としての製品の評価のためであったり、納入先への証明であったり、製品の仕様であったりとこれまでご相談いただいた内容は様々ですし、 海外からの納入品についての評価(ロットで品質が変わっていないかの確認など)もありましたので、主な素材、求められる評価内容、規格の有無など、 全体的に考えるご対応をさせていただきます。
そして、評価目的をはっきりさせた上で、双方で相談・検討をし、試験方法、評価項目などを決めて行くこととなります。
例えば、「建材」でも目的によって、製品が求められる耐候性を保持する期間は、10年であったり、20年であったりと様々ですし、 使用状態(屋外、室内、特殊現場)の設定も必要ですし、設置地域などによって設定する日照時間なども異なったりしますし、本当にいろいろなことを考慮する必要があります。
ですので、納入先さんから耐候性を求められた際、「どうしたらいいのか?」でしたら、まず「相談」をいただくことが一番近道と思います。
ご相談いただく内容は簡単なものから、検討をしっかり重ねないといけないような難しいものまでございますので、どこまで求められる評価とできるかは、相談・検討にかかってきますが、 そこにこれまでの知見の蓄積が活きてくると思います。
Q4今後の活用に向けPRをお願いします。
(丹羽)
当研究所に入ってこれまで25年間この評価に携わっています。もともと専門は、微生物による排水処理などでしたが、平行してずっと関わってきました。
ご案内のとおり、とても難しい評価なのですが、今は何でも劣化評価として見る必要があると思いますので、何にでもチャレンジしていくつもりです。
また、規格化についても、道路の舗装材などで関わった経験もあります。社内の製品検査・評価に関する標準づくりのお手伝いもしていますので、まずは「ご相談」こそと思っています。ご連絡よろしくお願いします。
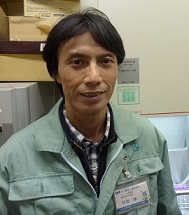
製品技術研究室 丹羽 淳 主幹研究員
取材後記
今回は、とてもマニアックな話題ですが、今後もなくてはならない、そしてとても難しい評価試験についてお話を伺ってきました。
信憑性を問われる評価においては何より経験とその蓄積が欠かせません。 地域で長年一つの評価技術に取り組んでこられた知識と経験を活用いただき、自社の劣化試験など評価方法をリニューアルされてはいかがでしょうか?
最新機器なども活用することで、これまでの評価がより効果的かつ効率的になるハズと思います。
本ページに関するお問合せ先
- 中部経済産業局 地域経済部 イノベーション推進課
- 〒460‐8510
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2774
メールアドレス:bzl-chb-sangi■meti.go.jp
※「スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。