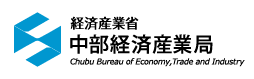アルコール事業法Q&A
最終更新日:平成26年10月9日
アルコールの使用許可を取得する予定、又は取得した事業所の担当者は必ずご確認ください。以下のQ&Aは、主として使用許可の内容となっています。
(1)制度全般
- アルコール事業法は、アルコールが広く工業用に使用され、国民生活及び産業活動に不可欠であり、かつ、酒類と同一の特性を有していることにかんがみ、アルコ ールの酒類の原料への不正な使用の防止に配慮しつつ、アルコールの製造、輸入及 び販売の事業の運営等を適正なものとすることにより、我が国のアルコール事業の 健全な発展及びアルコールの安定的かつ円滑な供給の確保を図り、もって国民経済 の健全な発展に寄与することを目的とする法律です。
- アルコール事業法では、事業者等に対する許可制を採用し、アルコールの製造、輸入、販売、使用について、許可を受けることにより一定の条件の下に自由に行うことができるとしております。一方、アルコール事業法に基づく流通管理になじまないケースに使用されるアルコールについては、「特定アルコール」をお使いいただくことになります。「特定アルコール」は、「加算額(*1)」を含むアルコールとして、製造事業者又は 輸入事業者から販売され、アルコール事業法の規制を受けることなく、自由に流通 することが認められています。
- アルコール事業法は、上記にあるアルコールの適切な流通体系を構築するため、許可制度の導入、アルコール使用簿作成の義務づけのほか、定期報告義務や立入検査等による事後チェック等、工業用アルコールの流通管理制度及び安定供給の為の措置が規定されています。
なお、アルコール事業法では、対象となるアルコールについて、アルコール分が90度以上 (温度15度時)のものと規定しています。 - (*1)加算額とは、アルコールが酒類の原料に不正に使用されることを防止するために必要な額として経済産業省令で定めるところにより計算した額(*2)。酒税相当額 と表現されることもあります。
(*2)経済産業省令で定める加算額(アルコール1KLあたり)
一.アルコール分が91度未満のもの 90万円
二.アルコール分が91度以上のもの 90万円にアルコール分が90度を超える1度ごとに1万円を加えた金額 - ◆参考:アルコール事業法に基づく制度のイメージ図
 (PDF:17.2KB/経済産業省サイト内)
(PDF:17.2KB/経済産業省サイト内)
- アルコールが酒類と同一の特性(致酔性)を有していること(制度上、酒類には酒税法により税金が課されている。)にかんがみ、アルコールの酒類への原料への 不正な使用の防止に配慮しつつ工業用に確実に供給されることを確保するため、加算額(酒税相当額)を含まないアルコールの使用に対し、以下の事項を定めております。
- A:許可制の採用
アルコールを工業的に使用しようとする者は、事前に 経済産業局長から許可を受ける必要があります。
申請においては、アルコールの使用方法についても許可の内容としており、当初の許可内容と異なる使用方法については、変更前に、変更許可申請により変更の許可を得ておく必要があります。 また、代表者や設備等、当初の許可内容と異なることとなる場合等には、届出等が必要になる場合がありますので、経済産業省がホームページで掲載している手引きを確認されるか、経済産業局まで問い合わせるようにしてください。
◆参考:アルコール事業に関するページ (経済産業省サイト内)
(経済産業省サイト内) - B:法定帳簿記帳義務
許可を受けてアルコールを使用する者にあっては、使用施設ごとに、度数及び発酵・合成の別に帳簿を備え、アルコールの移出、移入、使用数量、製造した製品等に係る項目を記載することが義務づけられています。 (帳簿は記載の日から5年間保存することが必要です。) - C:事業者からの定期的な報告
毎年1回5月末日までに、前年度におけるアルコールの譲受け数量、使用数量、製品等の出来高等を記載した報告書を経済産業局長に提出することが義務づけられています。 - これらの事項に違反した場合、行政処分・罰則の対象となりますのでご注意ください。
- そうした場合は、特定アルコール、又は、アルコール製剤を使用する方法が考えられます。
特定アルコールとは、加算額を含む価格で譲渡されるアルコールで、自由に使用することが可能となっており、許可を受けて行う必要もありません。
また、メーカーで製造されたアルコール製剤を購入、使用するという方法もあり、アルコール製剤を使用する場合もアルコールの使用許可申請や管理は不要です。
- 特定アルコールは、製造事業者、輸入事業者が特定アルコールとして譲渡した後は、自由に販売、使用することが可能となっています。 また、アルコール製剤については、ホームページ等により販売先やメーカーにお問い合わせ下さい。
- アルコール事業法の許可を取得した事業者(製造・輸入・販売・使用)の名簿は以下のホームペ-ジで確認することができます。
◆参考:アルコール事業法の許可を取得した事業者(製造・輸入・販売・使用)名簿 (経済産業省サイト内)
(経済産業省サイト内)
- アルコール事業法では、違反行為等に対しては、業務改善命令、許可の取消しと いった措置のほか、罰則も定められています。
また、アルコール事業法では、許可事業者に対し、確認のための報告徴収や立入検査についても規定されております。 (関係法令リンク)
◆参考:アルコール事業 > 関係法令 (経済産業省サイト内)
(経済産業省サイト内)
(2)手続き関係
- アルコールを工業的に使用しようとする者は、申請書に添付書類を添えて、経済産業局長に提出して許可を受ける必要があります。
申請の前には経済産業省がホームページで掲載している「アルコール使用の手引き」をよくお読み下さい。
※なお、許可を受けたときは、登録免許税がかかります。(使用許可の場合、1万 5千円)
◆参考:アルコール事業法手続マニュアル > アルコール使用の手引き (経済産業省サイト内)
(経済産業省サイト内)
- 添付書類については、「アルコール使用の手引き」(手引きについてはQ7参照) に説明がありますが、主なものとしては、以下の書類をご提出いただきます。
- ・ アルコールの貯蔵設備等の構造図等(アルコール貯槽や危険物倉庫等の構造 図)
・ 使用に係る設備の名称及び能力一覧、貯蔵設備の容量及び基数一覧、計測機 器の名称、形式及び基数一覧、移送配管内の容積。
・ 使用設備、貯蔵設備等の配置図及び使用施設毎の図面(上記設備等が配置図上や図面上のどこに所在するかを明示していただきます。)
・ アルコール使用明細書(アルコールの使用方法を記載したもの)
・ 誓約書
・ 登記簿謄本(個人の場合は住民票)
・ 定款又は寄付行為
- 変更許可申請書を、事前に提出し、変更許可を受ける必要があります。経済産業局に変更内容を伝え、ご相談下さい。
◆様式:様式第52(アルコール許可使用者許可事項変更許可申請書) (アルコール事業法に関する申請様式等/経済産業省サイト内)
(アルコール事業法に関する申請様式等/経済産業省サイト内)
- アルコールを許可した範囲を超えて使用する場合は、事前に変更許可申請を行うことが必要です。許可使用事業者は手続きを失念しないようご注意ください。
◆様式はQ9と同じです。
様式:様式第52(アルコール許可使用者許可事項変更許可申請書) (アルコール事業法に関する申請様式等/経済産業省サイト内)
(アルコール事業法に関する申請様式等/経済産業省サイト内)
- 変更届出書の提出が必要です。
ただし、代表者の変更は登記簿謄本を添付し事後遅滞なく、主たる事務所の所在地の変更は、事前に変更届の提出が必要ですのでご注意ください。
◆様式:様式第53(アルコール許可使用者許可事項変更届出書) (アルコール事業法に関する申請様式等/経済産業省サイト内)
(アルコール事業法に関する申請様式等/経済産業省サイト内)
- 原則、廃棄には、事前に届出が必要であり、経済産業局職員の立会のもと廃棄することが必要です。
特に、産業廃棄物業者へ引渡を行う場合は一定の処理が必要な場合がありますので、早めにご相談下さい。
◆様式:アルコール廃棄処分届出書<「使用の手引き」中の申請及び届出書様式を抜粋>
(アルコール事業法に関する申請様式等/経済産業省サイト内)
(3)帳簿・定期報告書関係
- 事業法施行規則や手引きで記載すべき事項が定められています。必要事項は以下のとおりです。
・ 帳簿は、アルコールの度数及び発酵・合成の別ごとに記載。
・ 移入したアルコールの数量、移入年月日、販売者の名称及び許可番号。
・ 移出したアルコールの数量、移出年月日、移出先事業場の名称。
・ 使用したアルコールの数量、使用年月日。
・ アルコールを使用してできた製品の名称、製品整理番号、製品出来高、製造年月日。
・ 欠減、亡失、盗難等の記録。
・ アルコール在庫数量 - アルコール使用簿の、様式は任意となっていますが、上記項目が確認できることが必要です。 また、記載のタイミングは、アルコールの搬入、アルコールを製造のため生産ライン等に払い出したとき(日)、製品等が製造されたとき(日)等、上記事項が記載可能となった後、 遅滞なく、その帳簿に記載しなくてはなりません。
- 1年間(4月1日~3月31日)記帳した帳簿の内容を取りまとめ、指定された様式に従い報告します。 具体的には、1年間のアルコール購入量、1年間の許可品目毎のアルコール使用量、1年間の許可品目毎の製品出来高、繰越在庫、アルコールの購入先などです。 この報告は、アルコールの買い受けや使用の実績がない場合でも報告書の提出が必要です。
- ◆様式:アルコール事業法の定期報告用の作成支援ソフトのダウンロードページ
 (経済産業省サイト内)
(経済産業省サイト内)
(4)立入検査関係
- アルコール事業の適正な運営を図るための措置として、経済産業局職員は、許可事業者の事務所、事業場に立入り、
機械・器具、アルコール貯蔵施設等の物件及び帳簿、書類等を確認、検査し、分析のため、必要な試料を収去する場合もあります。
検査においては、許可事業者が法に定められた流通管理を行っているかの確認になりますので、アルコール使用簿により適正に管理されているか、 使用方法が許可の範囲内であるか等について確認を行うこととなります。
このページに関するお問い合わせ先
中部経済産業局 産業部 産業振興課 アルコール室
住所:〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2785
FAX番号:052‐951‐0977