
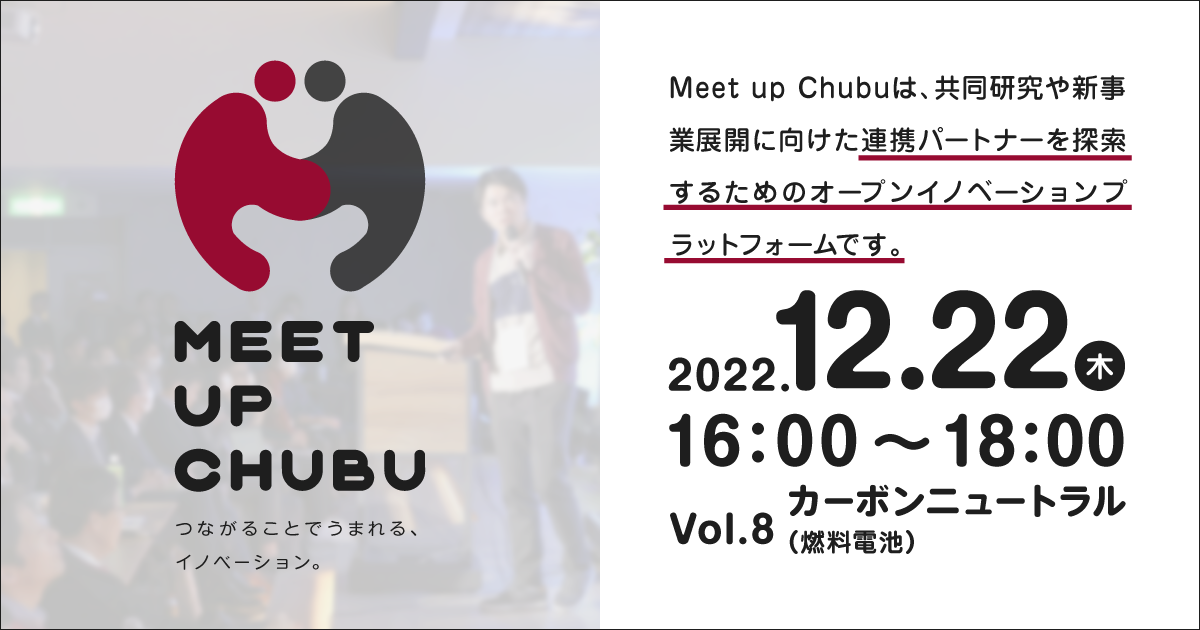
『Meet up Chubu 』vol.8 カーボンニュートラル(燃料電池)
<開催概要>
◇日時:2022年12月22日(木)16:00~18:00
◇対象:共同研究や新事業展開など協業先探索にご関心のある方
◇会場:ナゴヤ イノベーターズ ガレージ アネックス(ナディアパーク3F)/オンライン(Microsoft Teams)
◇主催:中部経済産業局、中部経済連合会
<プログラム>
※講演資料につきましては、複製および転載無きようお願い申し上げます。
●「世界に伍するFC生産技術の課題と未来」
技術研究組合FC-Cubicは、燃料電池システム企業と燃料電池基盤技術の研究を進めている大学及び産業技術総合研究所が参画し、
2010年4月2日に設立、産業技術総合研究所臨海副都心センターを拠点として活動しております。
現在は、組合員 39企業、1行政法人、5大学と拡大しております。
エネファームやFCVの本格的普及、また、期待される新たな分野への燃料電池の拡大のためには、
技術革新による画期的な燃料電池システムの低コスト化と大幅な耐久性・信頼性向上等の高次元での両立がまだまだ必要です。
今回は、FC-Cubic参画企業から大学・研究機関・企業のみなさまに、燃料電池(FC)の『高効率生産』『高品質管理』を
追求するうえでの生産技術面の課題や、お力添えいただきたいことを発信いたします。
(1)「FC生産技術 世の中の動向 および 国内メーカ課題」
技術研究組合FC-Cubic 特命研究員 佐藤 克己 氏
FC生産技術のトレンドとして「製造スピード改善」や「材料ロス低減」による「高効率生産」、「高品質管理」、「原料プロセス低コスト化」と いったことが求められつつあります。特に我々FC産業界としましては、「高効率生産』と「高品質管理」を追求する必要があると考えます。 本発表では、我々FC産業界の海外動向と現状をご紹介しつつ、国内のFC生産技術を比較して、解決すべき課題や革新すべきことを説明させていただきます。 また、スタック工程の中で各社の悩みの大きいエージング工程についても説明させていただきます。 今後、学会等でご関心ある大学、研究機関、企業のみなさまとの協業を希望しております。

佐藤様ご講演資料はこちら![]() (2,759KB)
(2,759KB)
(2)「FC生産技術課題1 MEAプロセス」
トヨタ自動車株式会社 商用ZEV基盤開発部
先端開発・技術連携グループ主幹 秋田 靖浩 氏
本発表では、インク調合とCCM、GDLと呼ばれる電極部材の塗布・乾燥、サブガスケット貼り合わせ・検査を行う工程
「膜電極接合体(Membrane Electorode Assembly:MEA)プロセス」における課題について説明させていただきます。
インク製造・保管~塗布~乾燥の各過程においては、性能/構造/材料・工法の各パラメータと電極構造、性能との定量的な
紐付けが必要です。また、搬送・貼り合わせ・検査においては、廉価な薄膜搬送補助用支持手段、および検査手段の開発が必要です。
これら課題に一緒に取り組んで頂ける方との繋がりを期待しております。

秋田様ご講演資料はこちら![]() (1,718KB)
(1,718KB)
(3)「FC生産技術課題2 バイポーラプレート/セパレータプロセス」
本田技研工業株式会社 生産技術統括部
パワーユニット生産技術部 パワーユニット生産技術管理課 小林 洋平 氏
燃料電池部品のバイポーラプレート(BPP)/セパレータの生産技術課題について、カーボンベースと金属ベースに分けて説明させていただきます。
カーボンベースとしては、圧縮成形・接着の生産性課題を克服する材料開発や微小クラックの代替検査方法の開発が望まれております。
金属ベースとしては、プレス成型品質と生産性を両立して高めること、耐久信頼性のある高緻密性薄膜成膜品質とセットで高速・廉価となる
表面処理工法が望まれております。その際、シール形成との界面設計や選択的表面処理なども考慮する必要もあります。
多岐にわたる工法を駆使して製造しているのが実情であり、さらなる進化に向けての生産技術課題に対し、みなさまのお力添えをいただけることを期待しております。

小林様ご講演資料はこちら![]() (1,866KB)
(1,866KB)
●「燃料電池用金属セパレータの実用化に向けての革新的生産技術の開発」
株式会社プラズマイオンアシスト 取締役会長 鈴木 泰雄 氏
当社では基材の表面改質等の要素技術開発をベースに量産装置の実証研究開発を行いました。成果としてSUS基材で当面の目標を達成しております。
実用化に向けて更なる量産性、長寿命化、低コスト化するには、 温度制御付き大容量プラズマ源の開発、コンタミ対策、基材の選定(SUS,Al)、
基材に見合った成膜プロセス、量産成膜 方式(R to R,L to L)の革新的生産技術の開発と評価技術開発が急務です。
共同研究及び事業化に向けた大規模実証実験への連携パートナーを探索しております。
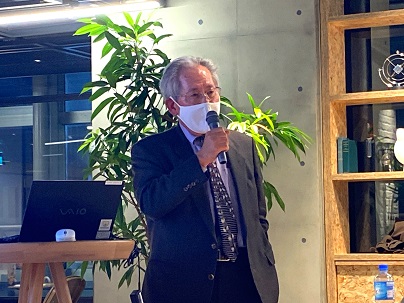
鈴木様ご講演資料はこちら![]() (1,971KB)
(1,971KB)
