

『MEET UP CHUBU』vol.57
モビリティ with Map NAGOYA
『MEET UP CHUBU』は、「共同研究、新事業展開に向けたオープンイノベーション(協業先の探索)」を
目的としたイベントプラットフォームです。このプラットフォームで
生まれた連携プロジェクトは、産学官からなる各種支援により社会実装の加速を目指します。
登壇者や追加テーマの募集は特設サイトにおいて随時行っています。
◇登壇や追加テーマ希望の方は『MEET UP CHUBU』特設サイトからお願いします。
こちらから
<開催概要>
◇日時:2025年2月13日(木)15:00 ~ 19:00
◇対象:共同研究や新事業展開など協業先探索にご関心のある方
◇現地会場:
ナゴヤ イノベーターズ ガレージ(ナディアパーク4F)
オンライン:Microsoft Teams
◇主催:中部経済産業局、中部経済連合会
●「Map NAGOYAの取組紹介」
一般社団法人中部経済連合会 価値創造本部 社会実装推進部
担当部長 森 連太郎 氏
産官学連携に繋げる為のマッチングイベントであるMap-NAGOYAを含めて、「次世代モビリティ」に関する中部経済連合会の取り組みについてご説明しました。
この取組みは、中部先進モビリティ実装プラットフォーム(CAMIP)を2021年5月に立ち上げて、本格的に開始したものです。
Map-NagoyaはMEET UOP CHUBUとの共催で今回が6回目を数え、今年度は、空モビリティにも活動領域を拡張し、従来の活動に加え、産官学での双方向コミュニケーションの活性化を図る活動を展開中と言及しました。

ご講演資料はこちら (2,030KB)
(2,030KB)
●「自動車産業の変化、先端技術研究所の役割と共創」
株式会社デンソー 先端技術研究所 先端研企画室長 小峰 重樹 氏
デンソーの先端技術研究所は、未来を見据えた技術を生み出すために取り組んでいます。社会が変化し、自動車産業も大きく変わりつつある今、研究所の自立性と自律性がますます重要になっています。
創立以来、私たちは新しい科学から技術を作り上げることに情熱を注いできました。そして今、技術を社会に繋げるための共創活動をさらに強化しています。基礎研究や応用研究はもちろん、技術や製品の共同開発、事業化のパートナーシップなど、さまざまな場面で共創を求めています。
「統合報告書2024」はこちら
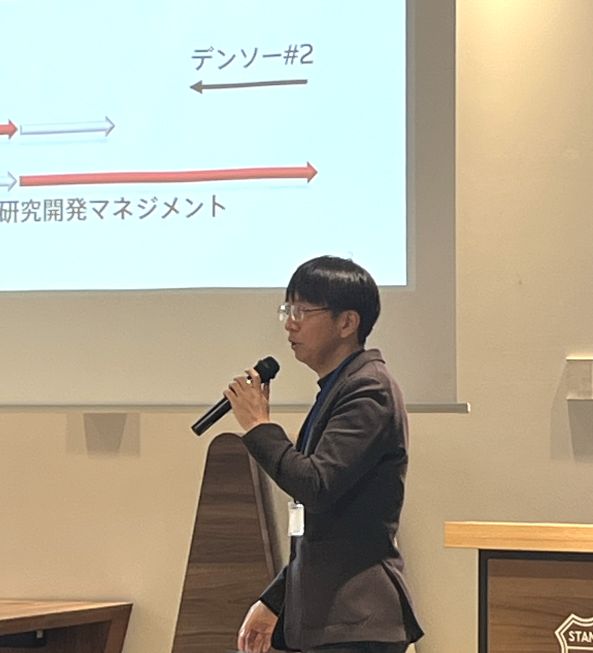
資料非公開
●「AIの機械学習における、コンピューティングコストの低減と、プライバシー・セキュリティの確保」
TieSet, Inc Sales Business Development Director 奥村 一雄 氏
TieSet, Incはシリコンバレーを拠点とする、分散学習のなかの連合学習技術のスタートアップ企業です。
AI活用において、下記が障壁になっておられる、製造業様・ロボットメーカ様・医療業界関・ヘルスケア関係者様、金融・保険業界の皆様とのアライアンスを希望いたします。
・AIモデルと学習の精度を上げる技術と知見
・学習コスト(サーバー側のコンピューティング・コスト)
・機械学習におけるプライバシーとセキュリティ
・AIモデルを最良の状態に保つ
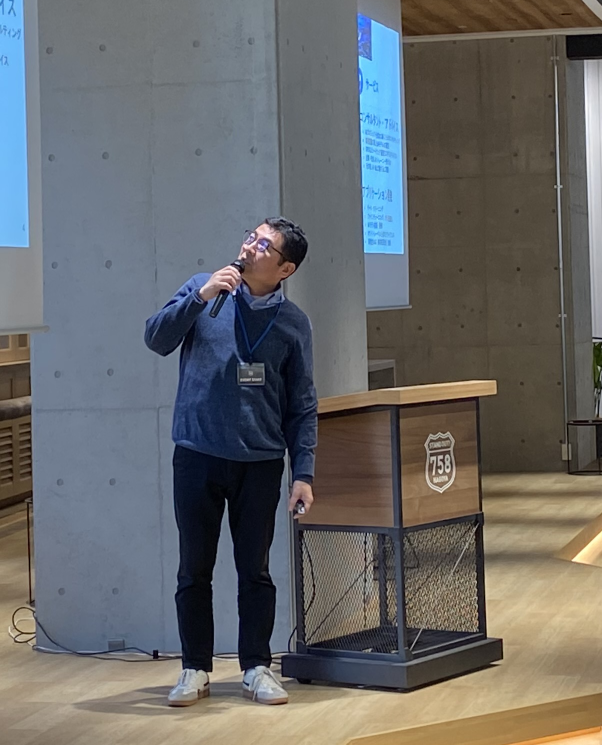
ご講演資料はこちら (2,618KB)
(2,618KB)
●「高齢ドライバ支援サービス実現に向けた取り組みの紹介」
名古屋大学 未来社会創造機構 特任教授
/株式会社ポットスチル 取締役 田中 貴紘 氏
高齢ドライバの事故低減・運転寿命延伸を目指し、エージェント/ロボットを活用する運転支援に関する研究成果や大学発ベンチャーの設立、および、社会実装に向け活動を進めている、他企業との取り組みについても紹介します。
自動車関連メーカーほか、地方自治体、交通事業者、損害保険会社との連携を希望します。
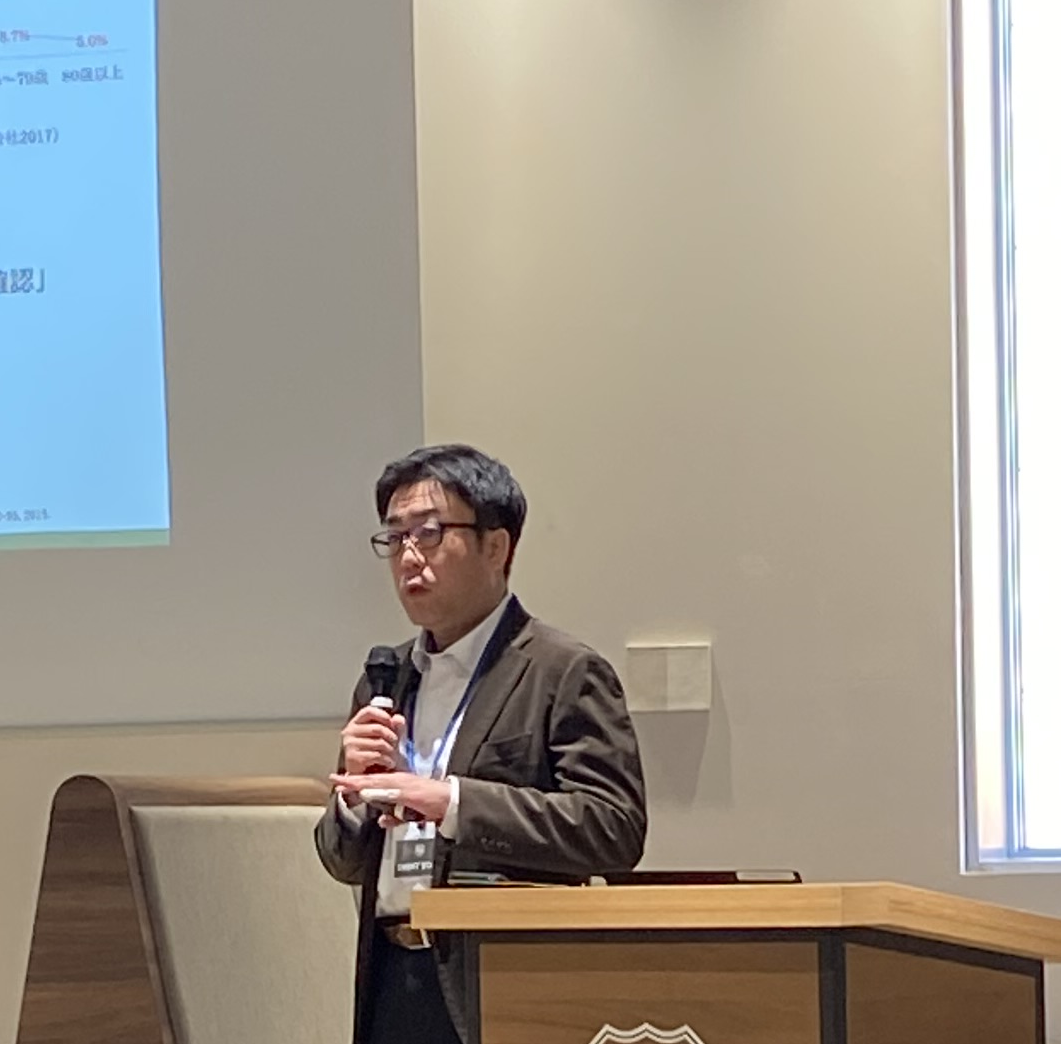
ご講演資料はこちら (2,920KB)
(2,920KB)
●「多用途eVTOL無人機に関する研究と今後の課題について」
中部大学 理工学部 宇宙航空学科 教授 棚橋 美治 氏
自律型無人機(ドローン)の活用が増加しています。
マルチコプタ型は、被災地の家屋内部や建造物の亀裂の調査等、迅速な低コスト運用が可能ですが、推力が自重保持に多く使われ、エネルギー効率の向上が課題です。
翼の揚力を活用した電動垂直離着陸(eVTOL)型は、任意の場所から広域長時間運用(被災地や離島への物資輸送等)が可能で高効率ですが、飛行制御の安全性確保が課題です。
今後、各種機関との連携により、実用化を図ります。
また、皆様のニーズに合わせた各種無人機のカスタマイズのご相談も承りますので、お気軽にご相談ください。

ご講演資料はこちら (6,667KB)
(6,667KB)
●「地域や企業の取り組みにみるモビリティのあり方」
名城大学 経済学部 准教授 太田 志乃 氏
国内「自動車産業」を取り巻く環境変化が確認されるなかで、ユーザーの利便性を高める取り組みにも注目が集まっています。
これら取り組みは、過疎地や観光地などその対象によって方向性は異なるものの、共通項は「その地域を知り、ユーザー利便性に沿ったモビリティの投入」です。
本報告では国内3地域の取り組みに注目し、これら取り組みが実装されるための条件を概観します。
地域自治体や地域活性化に向けた事業を展開する企業からのご意見を希望します。

ご講演資料はこちら (4,027KB)
(4,027KB)
●「モビリティの電力消費を抑えるパワー半導体用結晶の評価技術」
一般財団法人ファインセラミックスセンター 材料技術研究所 機能性材料G
特任主幹研究員 石川 由加里 氏
パワー半導体結晶品質の非破壊・高速・大面積評価技術の開発を目指しています。
半導体結晶には残存する欠陥が多く、信頼性・寿命等に不安があります。本問題の解決には素子性能に影響を及ぼす欠陥を避ける必要があります。
しかし、検出すべき欠陥種や適切な評価技術は結晶種毎に異なります。各結晶の特徴に合わせた非破壊の評価原理を見出し、高速かつ大面積の評価へ向けた技術の原理検証が求められています。
上記評価技術を必要とする企業や検査装置メーカからの委託研究、大学・研究所との共同研究としての連携が可能です。

資料非公開
●「モビリティ部品のミニマル・サーキュレーションに向けて ~モータリマン~」
国立研究開発法人産業技術総合研究所 極限機能材料研究部門
副研究部門長 高木 健太氏
今後の製品開発においてサーキュラーエコノミー(CE)の検討は避けられなくなってきます。
特に、製品の競争力強化のためには、低環境負荷・高資源循環率・高性能を並立した開発が重要であり、その戦略の一つがリマニュファクチャリングなどのミニマル・サーキュレーションです。
CEは一つの企業や研究機関では成立しませんので、産総研ではモータを代表例としたCEに関する技術開発や仕組みづくりとともに、企業様との仲間作りも行っています。
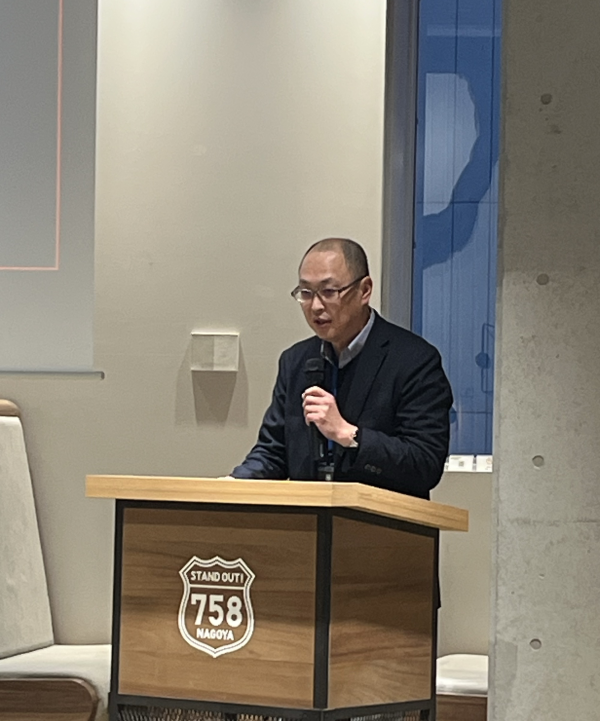
資料非公開
●NEDOの取り組み紹介(1)
「アカデミアの皆さんニーズあります、産業界の皆さんシーズあります
~NEDO Connect【シーズ発掘・育成!NEDO提案公募事業について】~」
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 フロンティア部
統括課長 植田 桂実 氏
NEDOでは、シーズ発掘・育成と産学連携を支援する提案公募型事業を通じて、大学や研究所、また企業が行う研究開発を支援しています。
研究開発をステップアップさせ、社会実装を早期に実現するためには、開発フェーズに応じた幅広いサポートが欠かせません。
新技術先導研究プログラム、未踏チャレンジ、フロンティア育成事業、官民による若手研究者発掘支援事業(若サポ)、懸賞金型活用型プログラム、脱炭素省エネ技術社会実装プログラムなど、NEDOのテーマ公募型研究開発事業を活用して技術の社会実装を目指しませんか。

ご講演資料はこちら (2,156KB)
(2,156KB)
●NEDOの取り組み紹介(2)
「未踏チャレンジ~新型直流遮断器によるeモビリティの安全革命~」
国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学大学院工学研究科 助教 兒玉 直人 氏
国立大学法人埼玉大学 大学院理工学研究科 准教授 稲田 優貴 氏
EVや電鉄、電動船舶、電動航空機をはじめとしたeモビリティの安全性を向上させる小型直流遮断器について、開発コンセプトや最新の研究成果などをご説明いたします。
昨今のeモビリティの大電力化に伴って困難となる安全性と経済性の両立を志向するメーカーおよびユーザー企業との連携を希望いたします。

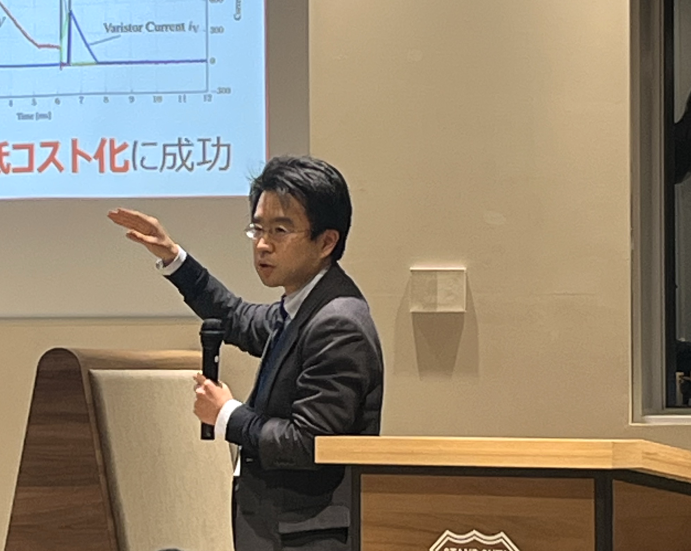
ご講演資料はこちら (3,971KB)
(3,971KB)
●「ネットワーキング」
登壇者や追加テーマの募集は特設サイトにおいて随時行っています。
◇登壇や追加テーマ希望の方は『MEET UP CHUBU』特設サイトからお願いします。 こちらから
◇対象:共同研究や新事業展開など協業先探索にご関心のある方
◇現地会場: ナゴヤ イノベーターズ ガレージ(ナディアパーク4F)
オンライン:Microsoft Teams
◇主催:中部経済産業局、中部経済連合会
担当部長 森 連太郎 氏
この取組みは、中部先進モビリティ実装プラットフォーム(CAMIP)を2021年5月に立ち上げて、本格的に開始したものです。
Map-NagoyaはMEET UOP CHUBUとの共催で今回が6回目を数え、今年度は、空モビリティにも活動領域を拡張し、従来の活動に加え、産官学での双方向コミュニケーションの活性化を図る活動を展開中と言及しました。
創立以来、私たちは新しい科学から技術を作り上げることに情熱を注いできました。そして今、技術を社会に繋げるための共創活動をさらに強化しています。基礎研究や応用研究はもちろん、技術や製品の共同開発、事業化のパートナーシップなど、さまざまな場面で共創を求めています。
「統合報告書2024」はこちら
AI活用において、下記が障壁になっておられる、製造業様・ロボットメーカ様・医療業界関・ヘルスケア関係者様、金融・保険業界の皆様とのアライアンスを希望いたします。
・AIモデルと学習の精度を上げる技術と知見
・学習コスト(サーバー側のコンピューティング・コスト)
・機械学習におけるプライバシーとセキュリティ
・AIモデルを最良の状態に保つ
/株式会社ポットスチル 取締役 田中 貴紘 氏
自動車関連メーカーほか、地方自治体、交通事業者、損害保険会社との連携を希望します。
マルチコプタ型は、被災地の家屋内部や建造物の亀裂の調査等、迅速な低コスト運用が可能ですが、推力が自重保持に多く使われ、エネルギー効率の向上が課題です。
翼の揚力を活用した電動垂直離着陸(eVTOL)型は、任意の場所から広域長時間運用(被災地や離島への物資輸送等)が可能で高効率ですが、飛行制御の安全性確保が課題です。
今後、各種機関との連携により、実用化を図ります。
また、皆様のニーズに合わせた各種無人機のカスタマイズのご相談も承りますので、お気軽にご相談ください。
これら取り組みは、過疎地や観光地などその対象によって方向性は異なるものの、共通項は「その地域を知り、ユーザー利便性に沿ったモビリティの投入」です。
本報告では国内3地域の取り組みに注目し、これら取り組みが実装されるための条件を概観します。
地域自治体や地域活性化に向けた事業を展開する企業からのご意見を希望します。
特任主幹研究員 石川 由加里 氏
半導体結晶には残存する欠陥が多く、信頼性・寿命等に不安があります。本問題の解決には素子性能に影響を及ぼす欠陥を避ける必要があります。
しかし、検出すべき欠陥種や適切な評価技術は結晶種毎に異なります。各結晶の特徴に合わせた非破壊の評価原理を見出し、高速かつ大面積の評価へ向けた技術の原理検証が求められています。
上記評価技術を必要とする企業や検査装置メーカからの委託研究、大学・研究所との共同研究としての連携が可能です。
副研究部門長 高木 健太氏
特に、製品の競争力強化のためには、低環境負荷・高資源循環率・高性能を並立した開発が重要であり、その戦略の一つがリマニュファクチャリングなどのミニマル・サーキュレーションです。
CEは一つの企業や研究機関では成立しませんので、産総研ではモータを代表例としたCEに関する技術開発や仕組みづくりとともに、企業様との仲間作りも行っています。
「アカデミアの皆さんニーズあります、産業界の皆さんシーズあります
~NEDO Connect【シーズ発掘・育成!NEDO提案公募事業について】~」
統括課長 植田 桂実 氏
研究開発をステップアップさせ、社会実装を早期に実現するためには、開発フェーズに応じた幅広いサポートが欠かせません。
新技術先導研究プログラム、未踏チャレンジ、フロンティア育成事業、官民による若手研究者発掘支援事業(若サポ)、懸賞金型活用型プログラム、脱炭素省エネ技術社会実装プログラムなど、NEDOのテーマ公募型研究開発事業を活用して技術の社会実装を目指しませんか。
「未踏チャレンジ~新型直流遮断器によるeモビリティの安全革命~」
昨今のeモビリティの大電力化に伴って困難となる安全性と経済性の両立を志向するメーカーおよびユーザー企業との連携を希望いたします。
